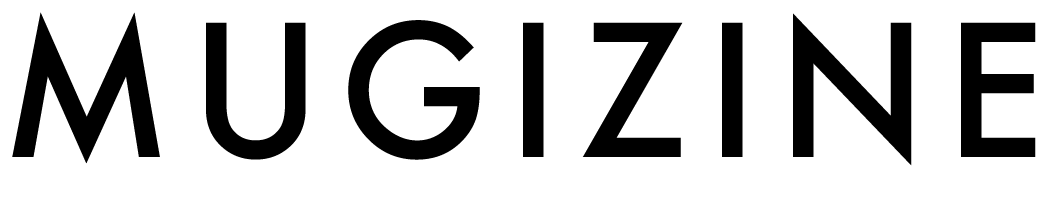徳島県海部郡牟岐町の青く澄んだ海を舞台に、新しい挑戦を始めた若い女性がいる。宮城京華さん(みやぎきょうか)、27歳。彼女はクラシックバレエ一筋で育ち、大学で世界の広さを知った。旅行会社で働いたのち、現在は牟岐町の地域おこし協力隊としてマリンレジャーの振興や海洋保護の活動に取り組んでいる。その歩みは、自然と導かれるように今へとつながっているように感じた。
15年のバレエが教えてくれたもの
——まずは自己紹介をお願いできますか?お名前や生まれは?
宮城京華(みやぎきょうか)、27歳です。徳島県の北島町で生まれ、大学卒業まで育ちました。
——大学まではどんな生活をしていらっしゃったのでしょうか?
小中高までは北島町内の学校に通っていて、幼稚園から20歳ぐらいまでずっとクラシックバレエを続けていました。
——クラシックバレエを?そんなに長く?すごいですね!どれくらいの頻度でやっていたのでしょうか?
はい、もう踊るのが大好きで。中学・高校の6年間は週6日で通っていました。学校が終わったらすぐにバレエスクールに通うといった感じの生活をずっとおくっていました。

——週6日ですか。それはもうバレエが生活のすべてだったんですね。ではプロバレリーナを目指していたのでしょうか?
はい。でも高校卒業したあたりでプロにはなれないなと感じて断念をしまして……それで四国大学に行くことにしたのですが、そこからもう2年間ぐらいはちょこちょこっと趣味でスクールに通ってっていう感じでした。
——へぇすごい。バレエの世界って凄そうですよね。映画やドラマの題材として扱われているのを観ると。表と裏のコントラストがすごいというか。
いやもうほんと、プロとして食べていくには一握りなのですごい世界なんだと思います。私はプロの世界に入ってないので実際どんな感じなのかは詳しくわからないのですが、私の通っていたスタジオは礼儀とか人間関係を丁寧に教えてくださる先生で、バチバチした感じはなくて、本当にみんなで切磋琢磨していってました。
——なるほど、バレエ一筋の青春時代だったんですね。
世界への扉をひらいた大学時代
——その後は四国大学に進学されたということですが、四国大学を選んだ理由などはあるのでしょうか?
本当は東京に出たいという夢が高校の頃からありまして。それで東京の大学に進学を目指してたんですけど、それは叶わなくて。それで地元の大学に行こうとなり、四国大学を選びました。
——叶わなかったというのは?
希望としてはプロのバレエ団に入るというのと、あと東京の大学でバレエ科があるところに行くという2択だったんですけど、プロのバレエ団に入れる程の実績はなかったので、断念しました。東京の大学の方もいくつか見には行ったんですけど、自分が納得するような大学が見つからなくて……で、もう本当に路頭に迷ってて高校3年生の時に。うーん……もうどうしようか……でもやっぱり大学は行こうかってなって思い、四国大学に行きました。
——四国大学では何を専攻したのでしょうか?
国際文化学科という科に行きました。そこで英語の先生の教員免許を取るコースにも行き、教員免許も取得しました。
——では、四国大学に入り、方向転換していったと。つまりバレエ一筋だった人生から違う道を模索しはじめていった先に教員があったと。
実は教員に興味があったわけではありませんでした。でも在学中に人生で初めて海外に行くという経験をしたんですが、バレエ一筋でずっと生きてきてたので結構視野が狭かったんですが、そこで一気に世界が広がって。
——海外に行くと世界が変わりますよね。その時、どの国にいったのでしょうか?
初めて行ったのはどこだったかな…あ、アメリカのワシントンD.C.に1週間、大学のプログラムで行って。もう本当に異文化でこんな世界があるんだ!みたいな。もっと世界の事を知りたいなっていう気持ちがそこで広がりました。
——他にもいろんな国に行かれたのでしょうか?
そこからは旅行でグアム行ったりシンガポール行ったりとかはあったんですけど……あと、2ヶ月間だったかな?交換プログラムでミシガン州にいきました、アメリカの。そこで現地のイマージョン・スクールで、日本語を教える先生を経験をして。その時に現地で日本語を教えるのと、徳島の文化を広めるというので、お遍路文化の徳島県内にある24のお寺の紹介をちょっとしたりとか。あと阿波踊りを子供たちに見てもらったりとか。そういうイベントとかも企画してやりました。

——では、バレエは諦めてなんとなく四国大学に行ってみたら、思いのほか楽しかったと。
思いのほかめちゃくちゃ楽しかったです。本当にすごい良い経験になりました。きっと大学に行かなくて国際文化学科を選んでいなかったら、この海外文化に興味を持つということもなかったなと思うので。
——その後は就職活動をするのでしょうか?
はい。旅行会社への就職を目指しまして、新卒で旅行会社に入社をしました。自分自身もやっぱりもっと色々な文化を知りたい、海外を見たいっていうのもありましたので。東京に本社がある旅行会社に入社して、大学卒業後は2年間東京で働きました。
コロナと共に始まった社会人生活
——就職を機に上京したんですね。
はい。でも入社したのが2020年4月でした。なので入社した途端にコロナ禍で休業になってしまったんです。海外団体旅行はすべてキャンセルになり、毎日がキャンセル処理の連続でした。一年ぐらいはそんな事務仕事をしていました。
——世界が大変な時期でしたからね。2021年になって少し落ち着いてきたころはそれらしい仕事はできましたか?
翌年は「Go To トラベル」という観光庁がはじめた観光業を支援するため政策がありましたが、それの事務局に出向していましたので、東京本社の仕事という仕事はあまり経験せずに時間が過ぎていってしまって……それで徳島にも支店があったので異動願を出して徳島に帰ってきたんです。
——徳島に帰ってきたかった理由ってなにかあるのでしょうか?
理由は若干彷徨っている感じになるんですけど(笑)、旅行会社に入ったけど自分が思い描いていた仕事ができてない。そこでもう1回自分が海外に出て視野を広げたいなという思いが出てきて、そこでワーキングホリデーに行ってみたいなと思い始めて。それで資金を貯めようと思い、帰ってきました。
——では、コロナがもしなかったり、もしくは活動が順調だったらそのまま東京にいた可能性が高かったいうか、宮城さんはそもそもそちらを望んでたんですね。
そうですね。東京でバリバリ働きたいというのがあったので、きっとコロナがなかったらそのまま東京にいたかもしれないです。

——そういった思いで帰ってきてからの活動はどのような感じだったのでしょうか?
帰って来てからすぐの試察研修で、観光局が主催をしている試察ツアーがありまして、そこに私が旅行会社の仕事として参加をしました。そこで牟岐町で協力隊をしていた石橋くんに出会いまして。2人とも海が好きだったので意気投合して、そこから交際がスタートしました。
石橋くんについてはこちら
——なるほど、交際をきっかけに牟岐に来ることが増えたわけですね。徳島出身なので牟岐町の存在は知っていたと思いますが、来たことなどはあったのでしょうか?
ほとんど来たことなかったです。小学校5年生に1回、宿泊学習で来たきりでした。でも徳島支店に異動してきてから、牟岐町に来る仕事が私の担当になりまして。なので試察ツアー以外でも牟岐に仕事でちょこちょこ来てて。そこで石橋くんとも会ったりしていたというのもあります。
海が導いた牟岐町との出会い
——海が好きだというのは幼少からのお話には出てきていませんが、実は海が好きだったと。
はい、好きでした。小学生の時に年に1回イルカと触れ合うような遊びに家族が連れて行ってくれてました。なので、海とかその海の生き物がすごい好きだったんです。中学校の修学旅行は沖縄で、そこで人生で初めての体験ダイビングをしたんです。そこでワッと海の見方が変わって、こんなに別世界なんだって感じました。
なので社会人になったらライセンス取ってみようかなって、中学生のときに思って。中学校のときに行ったショップにライセンスの金額表が書いてあったんですけど、結構金額が高くて……これは社会人にならないとなかなかできない遊びだなっていうのをその時思って。じゃあ社会人になった時の夢として1つ持っておこうと思ったんです。
——では、社会人になったら仕事をしながら、趣味としてダイビングをしていきたいと考えていたと。
コロナ禍のときは友達と旅行するなどもダメな時期でしたので、一人旅をスタートしてその旅先として沖縄を選んで、そこでライセンスを取ってっていうのをやってました。なので東京にいるコロナ禍のときにダイビングを趣味としてスタートさせて、こっちに帰って来るまでの2年間で沖縄に遊びに行ったりしていました。
——そこで海のアクティビティやダイビング関係を仕事にするのもありかな?みたいことは、どこかで感じたりしましたか?
ちょこっと思ったりはしていました。一人旅で沖縄に行った時に今の私のダイビングの師匠に出会いまして。その方にも本当にお世話になって、ライセンスをどんどんレベルアップさせていって、プロ資格まで取得できたので、これを将来的に旅行と掛け合わせたような形で、例えばたダイビングツアーみたいな形でできるようになったら最高なのかなっていうのは思っていました。
——でも旅行会社はやめることになると。
修学旅行とかの団体のお世話をしてる時に、添乗員をしていたのでコロナの感染があったりして、「あ、これはちょっと危ないな……」と感じまして。今のこの時期に旅行会社じゃなくてもいいのかなっていうのをちょっと思ってしまって。それで転職をしました。
——転職したんですね。
フルリモート、パソコン1台でできる人材系の会社に入りました。東京に本社があり、徳島で仕事ができたのでそれをしていました。パソコン1台で仕事ができるようになったので、牟岐にも来たり、あとダイビングのプロになるためのライセンス講習で必要な時は沖縄に飛んだりしながら生活をしていました。
——ではリモートの仕事を選んだというのも、そうしたライセンス取得をする理由が大きかったんですね。
まさにそのためにリモートできる仕事を選びました。今はインストラクターの資格の一番初期の段階のモノを取得しました。ここからまだ後ろにかなり資格があるんですが、今私が持っている資格でショップとか、お客様のガイドはできる資格なので。とにかくこの資格を取りたかったんです。

遊びから暮らしへ、牟岐の海が導いた移住
——その後、人材系の会社をやめて、地域おこし協力隊として牟岐町に移住することになるわけですね。
石橋くんと交際していく中で、ずっと牟岐町に住みたいなって思うようになりまして。この町の海が大好きだし、牟岐の人たちもすごくあたたかいので、やっぱりこれから先もこの海で遊びながら生きていきたいねっていう話を二人でしていて。
では現実的に、この町で自分たちがどんな仕事をしていったら良いかっていうのを考えた時に、今はまだ難しいんですけど将来的にダイビングショップとかゲストハウスとかをできたらいいねって話をしていまして。その夢を叶えるためにはどうしたらいいかな?じゃあ地域おこし協力隊になり、3年間でこの町の人たちと関わりながら、人脈を広げたりとか、あとマリンレジャーを盛り上げていくような活動をしたいなと思い、地域おこし協力隊になりました。
——移住する前…つまり旅行会社に勤めている時も、牟岐町でマリンレジャーはされていたのでしょうか?
はい。遊びでですが海に潜っていました。
——その時の体験がすごく魅力的に感じ、これから先も牟岐町に関わっていきたいという思いが芽生えたということでしょうか?
木村さんとか石橋くんと遊びに行き、海に潜り、海に行くたびにこんなに生命豊かな生き物たちがいっぱいいる海って、なかなかないなと感じまして。沖縄の海もすごく綺麗なんですけど、またそれとは雰囲気がガラッと違って楽しみ方が全然違うんです。牟岐の海は。魚の種類とか数はこっちの方がいいんじゃないかなと思うぐらいなんです。
木村さんについてはこちら
——へえ、そうなんですね。意外ですね。沖縄の方が豊かそうだと勝手にイメージしてしまいますが。
マスク、フィン、シュノーケルをつけてのただの素潜りですけど、見応え抜群で魚の大群とかもいるんですよ。
——例えば場所だとどのあたりの海でしょうか?
よく連れて行ってもらったのが牟岐大島です。木村さんの小さい船で海が良い時に連れて行ってもらって。で、2時間ぐらい遊んで写真とか撮って帰ってくるみたいな遊びをしていました。

——なるほど、牟岐大島ですか。あそこはスケール感がすごく、入江はとてもきれいですよね。もっと近場で自分の足でアクセスできるような場所では遊んではいないですか?
そうですね、今でこそ松ヶ磯(モラスコむぎの目の前の浜)で泳いだりするようになりましたが、あんまり遊んでいないかもしれないです。
協力隊として“海をひらく”日々
——現在は地域おこし協力隊として活動しているわけですが、具体的に活動はどういったことをされているのでしょうか?
主に2つの柱がありまして、1つはマリンレジャーの復興です。マリンレジャーを盛り上げていこうっていうことで、一先ず今年の7、8、9月は1回ずつシュノーケリングのイベントを行っています。子どもたちとか親子向けに牟岐の海を知ってもらう、実際に牟岐大島に行き、こうやって泳いでみよう!などといった具合に開催しています。この魚がいるよとか漁師さんたちを呼んで、今の海と昔の海の違いなどをお話ししてもらったりといった事をしています。

あと漁師さんたちと連携して盛り上げようっていうので、今年の7月に漁師さんにシュノーケリングガイドのプロ資格を取っていただいて。それでガイドとして今後一緒に活動をしていけたらと考えています。
そのガイドのプロ資格を取るのに救急救命の講習を1日と、あと私がシュノーケリングガイドの講習を2日間実施して。その3日間受けていただいたらプロの資格が取れるような仕組みなんです。
——へえ。希望した漁師さんが取得すると。
そうです。私たちがお声掛けをして。それで興味を持ってくれた漁師さんに取っていただく流れです。普段は結構漁で忙しいという話を聞いていたんですが、夏はあんまり漁が盛んじゃないということだったので。将来的に夏の漁師さんたちの1つの新たな収入源になってくれたらすごく素敵だなと思いまして。
漁師さんたちは本当にこの海の事を知り尽くしてるので、もうこれ以上に心強いガイドさんはいないかなと思っていまして。是非多くの漁師さんと連携できたら嬉しいなと考えています。
あともう一つ活動していることがあります。海洋保護の視点から活動をおこなっていまして、海洋プラスチックは世界的に問題になってると思います。牟岐にもそうしたゴミがたくさん漂着してきてるので、それをビーチクリーンで拾い、洗い、色別に分けて、ちっちゃく粉砕して乾燥して、すると小さいカラフルなパーツができるんですよ。それを使って子供たちにキーホルダー作ろうとか、あとコースター作ってみようといった活動をおこなっているんです。
 ▲黒潮の影響で、牟岐の浜には漂着ゴミが流れ着く。大潮や台風の後なら尚更だ。
▲黒潮の影響で、牟岐の浜には漂着ゴミが流れ着く。大潮や台風の後なら尚更だ。
 ▲彼女は牟岐に移住してから漂着ゴミを拾うことがライフワークとなった。
▲彼女は牟岐に移住してから漂着ゴミを拾うことがライフワークとなった。
 ▲拾ったゴミを色分けして選別し、ミキサーにかけて細かくし、再活用できるようにしている。
▲拾ったゴミを色分けして選別し、ミキサーにかけて細かくし、再活用できるようにしている。
 ▲お陰で事務所はすごいことになっていた(笑)
▲お陰で事務所はすごいことになっていた(笑)
 ▲イベント時にはこうしたコースターなどを参加者と制作している。
▲イベント時にはこうしたコースターなどを参加者と制作している。
ゴミに新たな価値を与えるアップサイクルは今全国的に広がってる活動なので、これを牟岐でもぜひ取り入れたいなと思いスタートをしました。
あと、小学校4年生の総合時間の授業で取り入れてくださって、ビーチクリーンに一緒に行って拾ったゴミで本のしおりを作ってっていうのをやりました。その中で牟岐の海はこういう魅力があるよとか、今こういう問題が起こってるよなどと、世界の海洋ゴミ問題の話をしながら、みんなで海について考えて、実際に体を動かして感じて体験するプログラムにしてます。
——つまり将来的にはマリンレジャーが漁師さんたちと良い形でつながり、結果それが牟岐の産業になればいいなという思いで、地域おこし協力隊として活動しているということですね。
はい、まさに。例えばマリンレジャーの会社だけが儲かる仕組みではなく、牟岐町全体がマリンレジャーで潤うような。町ぐるみで連携してできるのが最高かななんてことを考えています。
——今、協力隊になられて何ヶ月ほどでしょうか?
2025年4月からなので、約4ヶ月です。
——主に活動しているフィールドは牟岐大島でしょうか?
今年はイベントをやっているのは牟岐大島です。ですけど来年は目の前のモラスコむぎの目の前とか、あと古牟岐の港とかを会場にして色々イベントをやっていきたいなとは考えています。
——協力隊の任期が終える3年後にはどうなっていたい、もしくは目標を掲げていたりするのでしょうか?
地域おこし協力隊の任期が終わる3年後には、牟岐でダイビング事業をスタートできれば嬉しいという野望はあります。
私の場合、協力隊になるときに自分から役場へ企画書を提出して立候補した形だったので、その時に漁協役員の漁師さんたちにも3年間の活動内容や将来の目標をお話ししました。「報連相をしっかりして出来ることからやってみ」と、お声がけをくれる漁師さんもいました。
ただ、協力隊になったからといって、ダイビング事業ができるという訳ではありません。
マリンアクティビティを地域に受け入れていただくためには、安全に楽しめる体制を整えること、漁業と海洋保護・マリンレジャーの両立を図ること、そしてルールや規定をしっかり整えていくことが大切だと思います。
まずは何より、地域のみなさんとの信頼関係を築くことを大事にしながら、できることから一歩ずつ取り組んでいきます。
——海での活動となると漁師さんたちとの兼ね合いもあると思いますし、時間がかかることでもあると感じます。簡単ではないことだと感じますが、牟岐町の大きな資源は海だと僕も思っています。今後の活動に期待しています!

かつて牟岐町にはダイビングショップが存在し、県内外から多くの人を集めていた時期があった。しかし、様々な事情からその灯は消え、町の海と人をつなぐ拠点は途絶えた。だからといって海の魅力が失われたわけではない。豊かな魚影や地元漁師の知恵、透明度の高い水中景観は今も健在である。
ただし、ダイビング事業は資源管理や漁業との調整が欠かせず、一足飛びに進められるものではない。だからこそ宮城さんは、一人の挑戦としてではなく「町ぐるみで未来につながる仕組みづくり」として動いている。シュノーケリング体験や海洋教育を通じて、町の子どもたちや観光客に「海と関わる入り口」を広げつつ、漁師や教育機関と連携しながら信頼を積み重ねている。
まちづくりに大切なのは、町全体で資源を守り、その価値を分かち合うことだ。過去の記憶を踏まえながら、「次の世代につながる形」をみんなで育てていくことが、これからの挑戦になる。その挑戦の先に、宮城さんがどんな未来を描いていくのか。町の人々と共に紡がれていく歩みに期待したい。