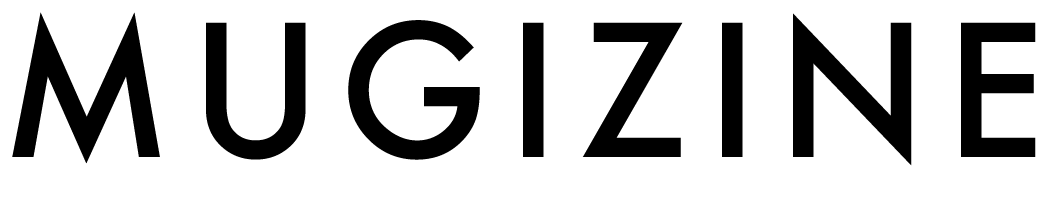今回お話を伺ったのは中山知華さん(20歳)。牟岐町生まれ牟岐町育ち、現在は徳島で大学生活を送っています。『NPO法人ひとつむぎ』が立ち上がった初期から運営側ではなく参加者として参加をし、現在は運営側として活動をしています。こどもの頃から牟岐を想い、積極的に地域活動をしてきた非常に稀有な存在といえるのかもしれません。そんな彼女に牟岐への想いを聞いてみました。
ひとつむぎとの出会いと関わり
ー 知華さんのご出身はどちらでしょうか?
生まれは牟岐町です。高校は阿南市の富岡西高に行っていました。
ー 高校で阿南市に行っていたのはなにか理由があったのでしょうか?
剣道が強い高校だったのでそこを選びました。兄も同じ高校で楽しそうやなぁと感じたのでそれもあります。
ー へぇ、兄弟で同じ高校に通っていたんですね。とても仲が良いんですね。高校進学の際に、県外へ行くという選択肢は考えなかったのでしょうか?
ー 剣道は武士道の真髄を究める道とも言えますが、そうした学びが魅力のひとつだったのでしょうか?
はい。小学校の時に「我以外皆師なり」という剣道において重要な教えを先生から教わって、中学校の時に作文を書いて全校生徒の前で読んだ事があります。私は「自分は頑張っている」という、どこか傲慢な部分があったりしたので、この言葉はそれを改めるキッカケを作ってくれましたし、挨拶をするなど多くの礼儀を学んだ事は今にも活きているなと感じています。
ー 牟岐町には『NPO法人ひとつむぎ』という、教育やまちづくりに携わる大学生を中心とした団体がいます。そことの関わりが知華さんは親密だとお聞きしていますが、ひとつむぎとはいつ頃から関わりがあるのでしょうか?
私が小学生の時だったかな?それぐらいの時がひとつむぎが発足をしたタイミングで、本格的に活動に参加をしはじめたのは中学生だったように思います。
ー 運営側ではなく参加側としてですね。そもそも、なぜひとつむぎに参加しようと思ったのでしょうか?
なんとなくといった感覚的なものですが、楽しそうだったんです。

ー へぇ。どのあたりが楽しそうと感じたのでしょうか?活動の内容が?
牟岐から新しい活動がはじまる!といった感覚あったので、それが良いなと思ったんです。楽しいことがこれからはじまる!みたいな。内容はというよりそちらの感覚的な方が強かったように思います。
ー 実際に参加してみていかがでしたか?
アイスブレイクとかをゲーム感覚でできて、とても楽しかった思い出があります。その時、何のために大学生が牟岐に来ているのか?とか、そうした事は全く考えていませんでしたが、大学生という存在が牟岐町にはほとんどいなかったので、ちょっと年上のお兄さんお姉さんたちと遊べるだけで楽しかった記憶があります。
ー そうした”楽しかった経験”から中学生、高校生の時にもひとつむぎに参加していくことになるのでしょうか?
はい、そうですね。最初はただ楽しいから参加していましたが、関わるうちに「町を盛り上げる活動」に少しずつ興味を持つようになっていきました。

交流授業で訪れた宮崎
ー 高校を卒業して大学に行くことになってから参加側ではなく運営側にまわることになるわけですが、ひとつむぎではどのような活動をしていたのでしょうか?
コロナ禍で出来なかったことなどが沢山あるのですが、一番印象に残っているのが2022年の大学一年の時に宮崎県の西都市のとある中学校に交流授業をしに行ったことです。それがとても楽しかったんです。
ー へぇ、どのあたりが楽しかったのでしょうか?
中学生たちがとにかく元気で驚きました。総合学習に力を入れている学校だったので、みんな発表のときにしっかりと自分の意見を伝えられるんです。校長先生も「子どもたちが自発的であること」を大切にしている方で、その姿勢が学校全体に根付いているのを感じました。朝には一緒に挨拶運動もしたんですよ。
ー 校門に立って「おはようございます!」とか「さよーなら」とかですかね?
そうです。帰る日の朝も、もう一度校門に行って挨拶しました。
ー 子どもたちとコミュニケーションを取る事が楽しかったんですね。
はい。それに、その中学校は規模的に牟岐町の学校と似ていたんですが、子どもたちの活発さがまるで違っていて、その違いがとても印象的でした。
ー 教育の違いを感じたのですね。
その時コロナ禍でしたのでとても難しい時期だったと思いますが、訪れた中学校は地域との関係を絶やさずにオープンにしていたのが良かったようです。あと宮崎という土地も良いなと思って。登って登っても平野で。そんな場所に行ったことなかったので。
ー 四国と九州の景色の違いですね。僕も平野の景色はとても好きなのでよくわかります。

大学での学びよりも地域創生
ー 大学は四国大学に行かれていると思いますが、そうした理由や経緯などはあるのでしょうか?
もともと県外に出るイメージがあまりなかったんです。本当は徳島大学の総合科学部に行きたかったんですが、残念ながら合格できず…。ひとつむぎで関わった大学生の多くが総合科学部の出身だったので、憧れがありましたね。結果として四国大学の経済情報学部・メディア学科に進学しました。
ー メディア学科はいかがですか?
カメラが好きで専攻しましたが一年生の時は座学ばかりで(苦笑)。二年生になったらようやくカメラを触れるようになり面白くなってきまして、今は映像とWebデザインを学んでいます。映像制作で15秒のCMを作ろうと思っていざ撮影してみたんですが、思ったより撮影に時間がかかって。撮影する前は絵コンテって必要ある?とか思っていたんですが、やっぱり絵コンテって重要なんだなーと(笑)。
ー 一年生の頃の座学の内容が、今になって理解できるようになってきましたか?
いえ…実はまだあまり実感できていないです(汗)。

ー え?そうなんですか(笑)。現在大学には通っているけれど、大学で学ぶことにそこまで興味はないように感じます。知華さんとしてはひとつむぎの活動の方が興味があるのでしょうか?
ひとつむぎの活動の方が全然興味があります。
ー それは自分の故郷である牟岐町をベースに活動をしているからでしょうか?
それもありますが、大学で映像編集をしていると、作業に時間がかかる上に基本的に一人で進めるので、孤独を感じることが多いんです。でも、ひとつむぎの活動で子どもたちと関わっていると、そういう孤独を感じることがなく、純粋に楽しいと思えるんです。
ー こどもが好きなんですね。
はい、こどもが好きなんです。
ー では教育にも興味があると。
教育には興味がありますが、より広い意味でいうと「地域創生」に関心があります。地域創生を考えたときに、教育は欠かせない要素のひとつだと思うんです。ただ、教育って成果がすぐに目に見えるものではないので、どうしても投資しにくい分野だと思うんですが、そこにしっかり取り組んできたのがひとつむぎや牟岐町なんですよね。だから、教育というよりも「地域創生の手段としての教育」に関心があります。

ー 現在大学三年生。これから就職活動をしてくことになると思いますが。
まだ何も決まっていなくて(汗)、どうするのがベストなのか悩んでいます。今までの活動を踏まえた上で、自分がどのポジションを取るのが一番良いのかを模索している段階です。
ー メディアについて学んでいるので、そういった関係には興味はないですか?
写真が好きなので写真家とかフォトグラファーになってみたいなとは思っています。でも写真館とかだと日曜日は仕事をしなければいけないので(笑)、違う形でできたらと思っています。
牟岐に残るのが理想
ー では最後に。ひとつむぎに参加したり、県外に出る考えがそもそもなかったりなど、牟岐町への想い…というか故郷が好きといった印象を受けているのですが、一方で宮崎が良かったなど、経験の中から生まれてくる「故郷との違いのギャップ」が悩みのタネになっているような気もします。
やっぱり愛着があるし、もともと人混みとか苦手で都会に行きたいというのもなくて。ただ田舎が好きで自然が好きなんです。自分の生まれた町で家族がいる町で、思い出が蓄積しているので牟岐町は大事な町です。現在、ひとつむぎや牟岐町の取り組みのお陰で牟岐町には大学生とか関係人口とかが増えていて、活性化している部分が間違いなくあると思いますが、耕作放棄地とかもまだまだ多く、土地は荒れていっているので、現実的に考えると問題は大きいなと思います。そこで町を捨てて外に出ていくことは簡単ですけど、先祖とか家族が大事にしているモノを私も大事にしたいと思っているので、現実的に対処していける方法を牟岐にいながら考えていきたいなと思っています。今の牟岐だったら色んな仲間がいるので出来そうな気がしています。
ー では就職とかでまだ悩んではいるけど、できれば牟岐に残ってそうした活動を行っていけたらということでしょうか。
それが一番の理想ですね。こどもたちが地域に愛着を持たないまま出ていく事とかはすごく寂しい事です。頭が良いとかよりも情の深い人たちが増えてくれたら良いなと思っています。

知華さんは言葉を選びながら自身の考えを伝えてくれました。その姿勢からは、「地元を愛する気持ち」と「外の世界を知ることで生まれる葛藤」が感じられました。牟岐町が好きだからこそ、地域の未来を考え、貢献したいという想いを持っていると感じます。しかし、宮崎での経験を通して「自分の町との違い」に気づき、より良くするためには何が必要なのかを模索しているようにも感じました。
また、「町を出ることは簡単。でも、先祖や家族が大切にしてきたものを守りたい。」そう語る知華さんの言葉には、地域に根ざしながらも、現実的な視点で未来を考えていきたいという強い意志を感じました。理想と現実の間で悩みながらも、牟岐町に残る道を模索する姿は、多くの若者が抱える「地元愛」と「新しい世界への興味」、そして「自分の生き方をどう社会に調和させるか」という普遍的なテーマとも重なります。
そしてこれは、知華さんだけの問題ではなく、牟岐町、さらには日本全体が抱える課題でもあると感じます。グローバル化が進む中で、故郷への想いが薄れつつある現代において、「先祖や家族が大切にしてきたものを、自分も大事にする」というごく当たり前の気持ちこそ、今こそ見直されるべき価値ではないでしょうか。知華さんの言葉を通して、その大切さを改めて考えさせられるインタビューとなりました。